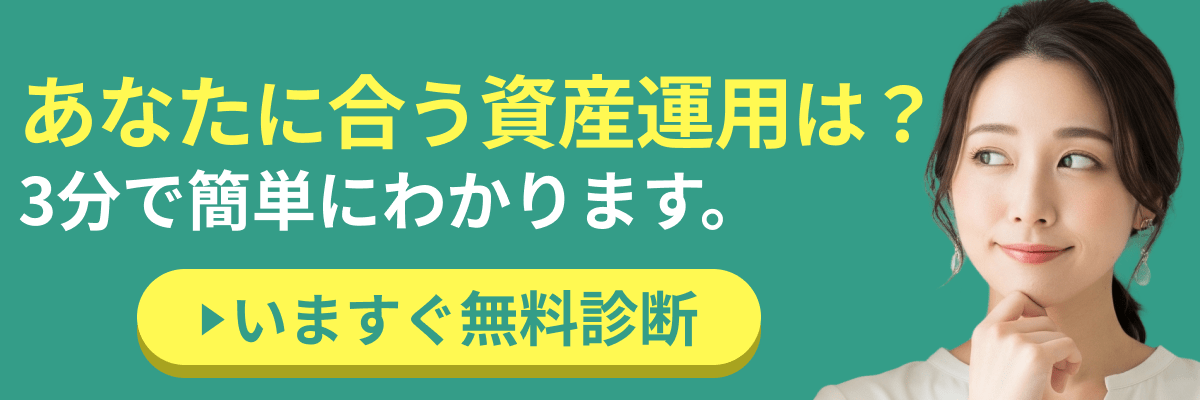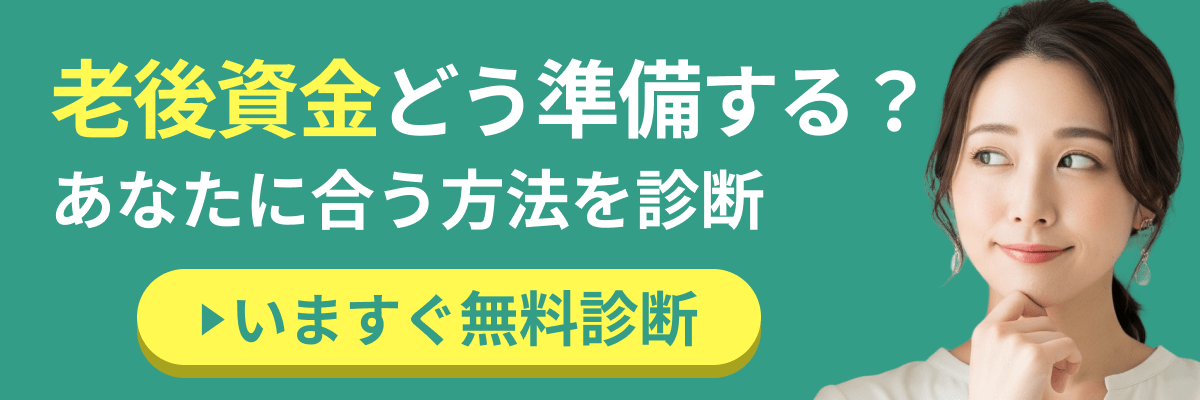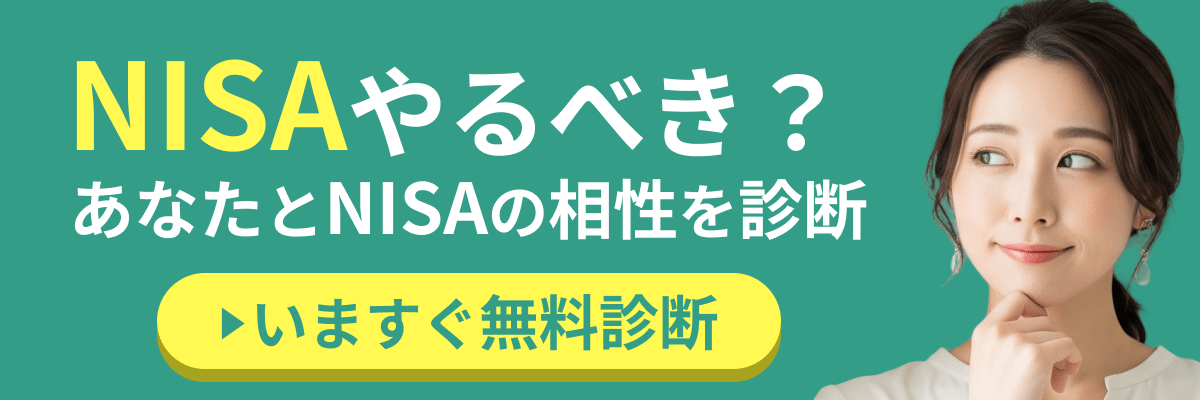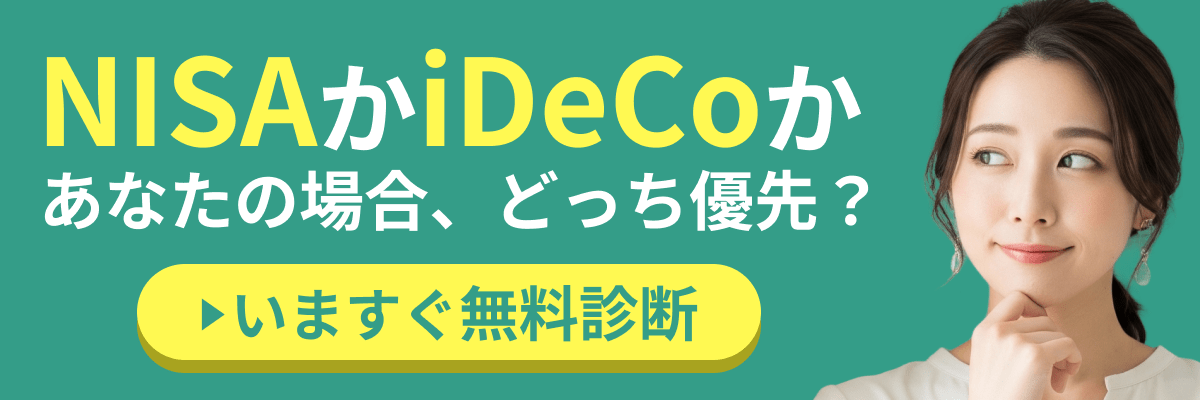海外資産に投資する際に気になるのが為替リスクです。
投資信託で「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」のどちらを選ぶか悩む方も多いでしょう。
そこでこの記事では、為替ヘッジの仕組みや、メリット・デメリットを詳しく解説します。
この記事を参考に、ぜひ自分に合った判断ができるようにしましょう。
【無料】今のあなたに最適な資産運用は?3分でシミュレーション
1. 為替ヘッジとは何か
まずは為替ヘッジの基本からおさらいしておきましょう。
1.1 仕組みと特徴
為替ヘッジとは、海外資産に投資する際に生じる円と外貨のレート変動による損益を小さくする仕組みです。
一般的には、対象となる外貨資産を買うと同時に、将来の売買レートを予約しておく「為替予約取引」などを活用し、為替差損益を相殺してリスクを抑えます。これにより、投資先の値上がり益を狙いつつ、為替相場の変動による不利益を軽減できるのがポイントです。この取引にはコストがかかるため、投資家は「ヘッジコスト」を負担することになります。
為替変動リスクをどう抑えるか
海外投資には常に為替リスクが伴います。日本円の価値が上がれば外貨建て資産の評価額が目減りし、逆に円安であれば外貨建て資産の円換算額は増える仕組みです。
そこで為替リスクを回避するために用いられるのがヘッジ取引です。あらかじめレートを固定することで、値動きが激しい相場局面でも、一定の安定した運用成果を得やすくなります。ただし、ヘッジをすることで得られるメリットとコストのバランスを常に考慮する必要があります。
2. 為替ヘッジにかかるコスト負担
2.1 コストの仕組み
為替ヘッジを行うと、通貨間の金利差を踏まえた「為替ヘッジコスト」の支払いや、逆に「為替ヘッジプレミアム」の受け取りが生じます。
例えば、米ドルと日本円では米ドル金利のほうが高いため、多くの場合ヘッジをかける際に金利差分をコストとして負担することになります。こうしたコストは、投資信託を長期で保有するほど蓄積し、運用成果に影響を与える点に注意が必要です。
金利差調整とは
金利差調整とは、投資対象国の金利と自国通貨の金利が異なる場合に発生するものです。基本的には高金利通貨を売る方がコストを負担し、高金利通貨を買う場合はプレミアムを受け取れる可能性があります。
例えば、ドル建て資産を円から買い、同時に為替ヘッジするケースでは、ドルのほうが金利が高いため差額を支払う形となります。この仕組みにより、取引不均衡が生まれにくくなるのが大きな特徴です。
2.2 コストがパフォーマンスに与える影響
為替リスクを抑えられる一方、ヘッジをかけるとコスト負担によって手取りのリターンが目減りする可能性があります。特に運用期間が長いほど、ヘッジ費用は積み重なり、パフォーマンスを圧迫する要因になることも否めません。
また、金利差が大きくなればコスト自体も増えるため、経済状況や金融政策によってヘッジコストは変動します。リスク回避のメリットと支払うコストが見合うかどうかを見極めることが重要です。
3. 為替ヘッジあり・なしのメリット・デメリット
為替ヘッジには、メリットだけでなくデメリットもあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
3.1 為替ヘッジありの特徴
「為替ヘッジあり」で投資信託を買うと、為替変動に起因するリスクを抑えながら海外資産の値幅取りを狙うことが可能になります。円高が進行した場合でも、ヘッジによって基準価額の下落をある程度回避できるため、価格変動がマイルドになる点はメリットだといえます。
ただし、ヘッジを行うにはコストが発生するため、長期の投資になるほど、為替差益が勘案されず、その分リターンは抑制されることになります。そのため、為替ヘッジは安定性重視の投資家に向いている選択肢だといえます。
3.2 為替ヘッジなしの特徴
一方、為替ヘッジなしの場合は、為替リスクを直接引き受けますが、その分コストは発生しません。円安に振れた時には外貨建て資産の評価額が上がり、追加の収益を得られるメリットがあります。
ただし、円高へ転じると受けるダメージも大きくなるため、基準価額が激しく上下に動く可能性が高まる点に注意が必要です。為替差益を積極的に狙いたい投資家、余分な手数料を抑えたい人に向いている選択肢といえるでしょう。
4. 円高・円安と為替ヘッジの効果
4.1 円高局面での利点
円高局面では、外貨建て資産が円換算で目減りするため、為替ヘッジなしの投資信託は価額が下がりやすくなります。一方、為替ヘッジありの場合は、ヘッジ取引によって円高時のマイナス要因を抑えられ、資産価値の下落幅を小さくできます。
したがって、短期間で円高に振れそうな相場感がある場合や、投資資金の変動幅をできるだけ安定させたい人には、為替ヘッジありが安心材料といえるでしょう。
4.2 円安局面での利点
円安に傾いた場合、為替ヘッジなしなら評価額が上振れし、差益を大きく享受できます。これに対して、為替ヘッジありだとせっかくの円安メリットを取り逃す可能性が高いといえます。
今後も継続して円安が進行すると見込むなら、あえてヘッジをかけずに大きなリターンを狙う戦略も考えられます。ただし、相場予測の難しさを踏まえ、常に円安が続くとは限らない点を念頭に置きましょう。
相場予測に頼りすぎない姿勢
為替相場は、専門家でも正確に予測するのはほとんど不可能です。短期的には、予期せぬさまざまな要因で上下しやすく、政治的要因や経済指標、金融政策次第で突発的な変動も十分考えられます。
そのため、為替がどう動くかの予測を決め打ちして判断するのは非常にリスキーです。自分のリスク許容度や投資目的から、ある程度幅をもたせた「可能性」を前提に為替ヘッジの要・不要を判断し、堅実な投資姿勢を心がけましょう。
5. 投資信託選びで大切なポイント
5.1 運用期間・目標別のヘッジ活用
為替ヘッジをどう活かすかは、投資期間や目的によって変わります。数年以内の短期運用で大きく損失を出したくない場合は、ヘッジありで為替リスクを抑えるのがおすすめです。
逆に長期運用で複利効果を狙い、コストを少しでも抑えたいなら、ヘッジなしを選択して為替差益を取りにいく方法もあります。
自分がいつ、どれぐらいの目的資金を必要とするかを踏まえ、ヘッジをどう活用するかを検討しましょう。
短期運用での注意点
短期投資は値動きの影響をダイレクトに受けやすいのが特徴です。為替リスクもその一つで、わずかなレート変動が損益を大きく左右することがあります。ヘッジありであれば、その変動を抑制できるため、大きな損失を避けたい方に向いているでしょう。
ただし、反対に急速な円安時に利益を伸ばすチャンスを逸する可能性もある点には注意が必要です。
長期運用での注意点
長期運用で為替ヘッジありを選ぶと、変動リスクを小さくできる反面、長期にわたってコストを支払い続けることになります。日本と海外の金利差が広がれば、ヘッジコストも大きくなり、リターン向上の足かせになるかもしれません。
逆にヘッジなしでは円高局面が来れば評価額が下がるリスクはありますが、円安の恩恵をフルに受けやすく、コスト負担も軽減できます。投資方針や心配性の度合いを踏まえて、どちらが自分に合うか見極めましょう。
6. 初心者向け・失敗しない投資信託の選定方法
ここでは、投資初心者の方に向けて、投資信託で失敗しないための選び方のポイントを紹介します。
6.1 投資目的の明確化
まずは「いつまでに、いくら必要か」を明確にするのが大切です。老後資金や教育資金、マイホーム資金など、使い道を意識してリスクの大きさを調整すると安心感が増します。これにより、ヘッジあるいはなしを選ぶ方針も見えやすくなるでしょう。
投資目標があやふやだと、相場の上下や情報に振り回されがちです。始める前に自分のゴールをはっきりさせるだけでも、意思決定はぐっと楽になります。
6.2 基本的なファンド選びの基準
投資信託を選ぶときは、まずどんな指標(ベンチマーク)を目標に運用しているかをチェックしましょう。S&P500のような株価指数を追うファンドなら、過去のリターンが比較的調べやすいはずです。
次に注目したいのが、運用実績や純資産残高です。一定規模の資産を集めているファンドは、投資家からの支持が得られている可能性も高く、途中で繰上償還になるリスクが下がります。さらに手数料も確認して、コスト負担を最小化できる商品を選ぶとよいでしょう。
ベンチマークを確認
ベンチマークはファンドの運用方針や目標リターンを把握する近道です。例えば、新興国に投資するファンドなのか、先進国の株式を中心に扱うファンドなのかによってボラティリティも異なります。
同じベンチマークでも運用会社や信託報酬に違いがあるため、似たようなファンドが複数ある場合は、費用面や運用実績を照合して総合的に検討しましょう。
過去の実績や純資産残高
投資信託の運用報告書を見れば、過去の運用成績や純資産残高の推移がわかります。投資家から資金が流出して純資産残高が小さくなると、繰上償還されてしまうリスクが高まる点に注意が必要です。
かといって資産規模が大きすぎるファンドも、柔軟な運用がしづらい場合があります。長期の視点で安定的な資金流入が続いているかどうかをチェックすることが、ファンドを選ぶ上での重要な判断材料となります。
投資対象と手数料のチェック
株式に投資するファンドなのか、債券中心なのか、あるいは複数の資産クラスを組み合わせたバランス型なのかによって、リスクとリターンは変化します。さらに、投資信託には購入時手数料や信託報酬、換金時にかかる信託財産留保額などが存在します。
似たようなファンドでも、これらの費用の差で長期的なリターンは大きく異なるため、必ず比較して負担を抑えられるファンドを選ぶようにしましょう。
6.3 迷ったときはプロに相談
「自分の運用方針に合った商品がわからない」「そもそもファンド自体の違いがよく見えない」といった場合は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やFPに相談するのも手です。彼らは特定の金融機関に属さず、中立的な立場でアドバイスを行えるのが特徴です。初心者にありがちな「無数の投資信託の中からどう選ぶか」という不安を解消しやすく、将来のライフプランに沿った資産形成の道筋を示してくれるでしょう。
7. まとめ
為替ヘッジは、海外投資で生じるレート変動リスクを抑えたいときに有用ですが、コストというデメリットも伴います。
選ぶポイントとしては、リターンを大きく狙いたいなら「為替ヘッジなし」、安定性を重視するなら「為替ヘッジあり」が基本となります。円高・円安は誰も正確に予測できないため、投資目的やリスク許容度、投資期間を踏まえて、慎重にどちらを選ぶかを検討しましょう。
投資信託を賢く選び、コストとリスクのバランスを取りながら長期的に資産を育てていきましょう。
マネイロ編集部