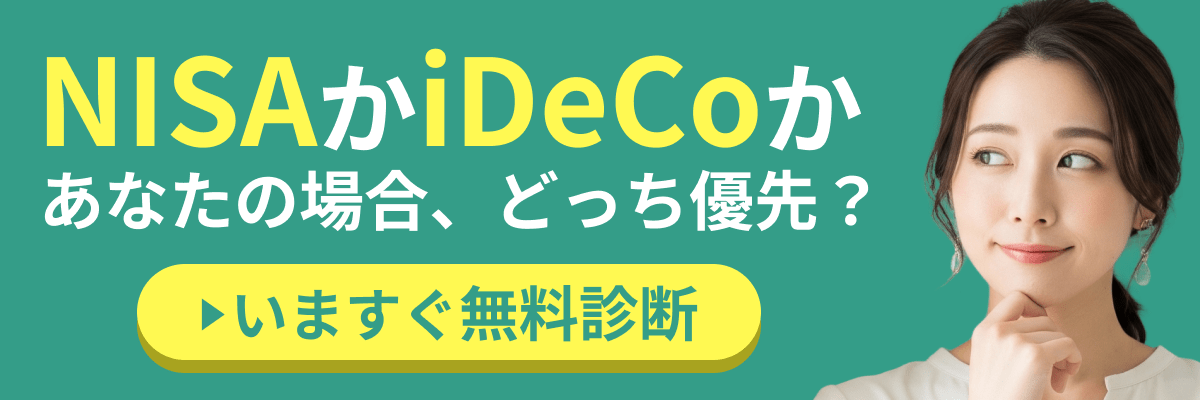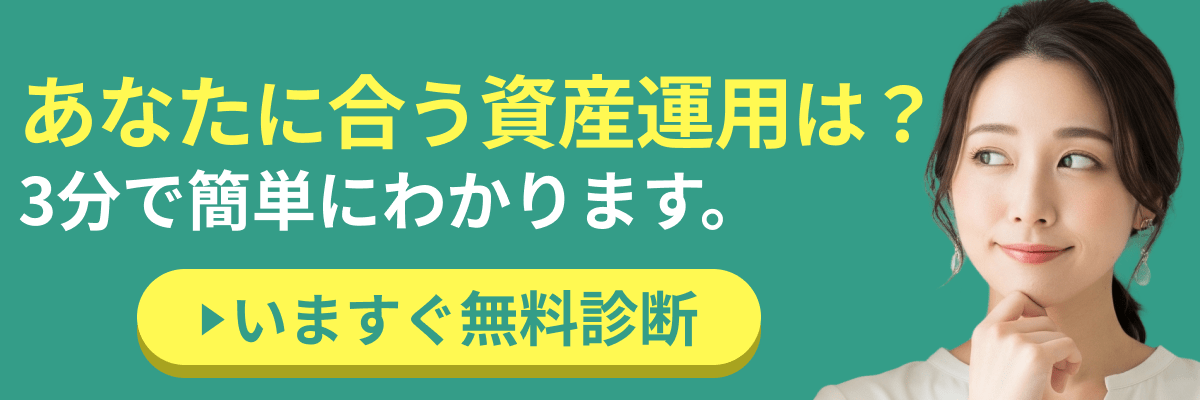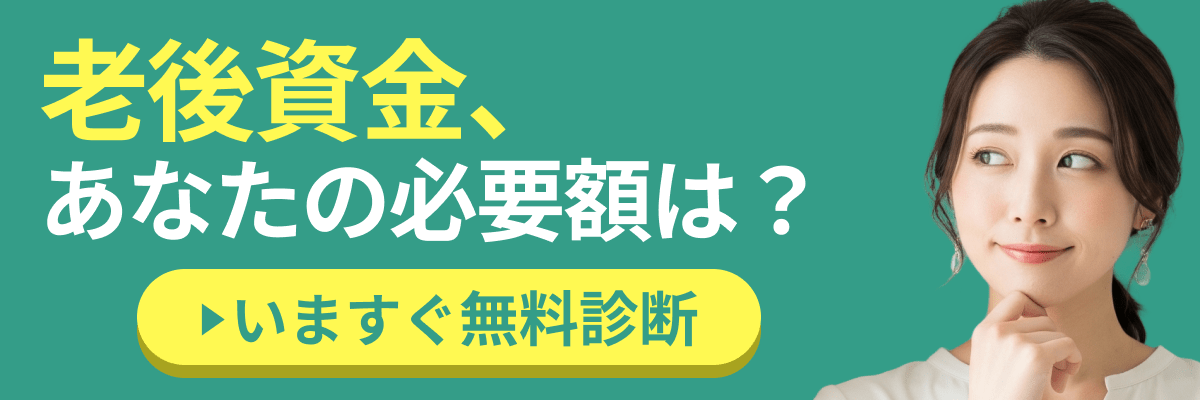老後に備えて、50代から資産運用を始めたいけれど、iDeCoとNISAのどちらを優先すればよいのかと迷う人は多いでしょう。
どちらも税制優遇がある資産運用に有利な制度ですが、運用期間や資金の引き出しルールが異なります。
そこで本記事では、50代がより安心して老後資金を準備するために、iDeCoとNISAの活用法や投資のコツをわかりやすく解説します。
【無料】あなたに向いているのはNISA?iDeCo?3分で診断
1. 50代でもiDeCoとNISAは始められる?
老後資金のための資産運用を考えたときに、iDeCoやNISAは有力な選択肢になります。そしてもちろん、50代からでもiDeCoやNISAは始めることができます。まずは、それぞれの特徴について押さえておきましょう。
1.1 それぞれの制度はどんな特徴?
iDeCoは将来の年金を自分で用意する「私的年金制度」で、65歳になるまで掛金の拠出が可能です。掛金すべてが所得控除となるほか、運用益も非課税となります。ただし、原則60歳まで引き出しできないため、資金拘束がある点に注意が必要です。
一方のNISAは18歳以上なら誰でも口座を開設でき、運用益が非課税になる制度です。いつでも解約できる流動性の高さが魅力です。
1.2 節税を重視するならiDeCo、自由に運用したいならNISA
iDeCoは掛金が所得控除されるため、収入が多いほど節税効果を実感しやすく、老後資金づくりにも直結します。
ただし、掛金の上限額が比較的低く、原則60歳まで資金がロックされる点がデメリットです。NISAはいつでも資金を取り出せる利点があるため、50代でも自由に投資を始めたい人に向いています。
2. NISA口座とiDeCo口座、利用状況は増えている?
2.1 50代でNISAを利用する人が増加中
日本証券業協会の集計によると、NISA口座の開設数は年々増えています。2024年12月末時点で、50代のNISA口座は約495万口座を超えており、買付金額も上昇傾向です。非課税枠を活かして将来に備えたいと考える層が着実に増えているといえるでしょう。
2.2 iDeCoの加入率も上がっている
運営管理機関連絡協議会のデータによれば、iDeCoの加入者総数は近年大幅に伸びており、2024年3月時点では830万人にも上っています。全体の34.1%を占めるほど普及が進行。うち、50代での加入者は232万人となっており、全体の28%を占めています。
【無料】あなたに向いているのはNISA?iDeCo?3分で診断
3. iDeCoの大きな利点は節税効果
3.1 掛金全額が所得控除になるメリット
iDeCoの最大の特徴は、掛金全額が所得控除の対象になることです。収入が多い人ほど税の軽減額が大きくなるため、短期間でも減税分を実感しやすいのが魅力です。さらに、運用益や受取時の一時金にも優遇措置があり、老後資金を効率的に形成しやすい制度といえます。
3.2 運用期間が短い場合の留意点
50代でiDeCoを始めた場合、拠出や運用に使える期間は限られます。長期投資ほど福利効果を得やすいものの、50代からだとリスクを取れる期間は長くはありません。掛金を設定する際は、無理ない範囲で拠出し、資金ロックのデメリットも踏まえておきましょう。
4. NISAのメリットは運用の自由度
4.1 投資がいつでもストップできる気軽さ
NISAは、投資の一時休止や売却がいつでも可能なので、ライフイベントに合わせて柔軟に対応しやすい点が特徴です。年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)の非課税投資枠内で運用しながら、必要に応じて資金化できるのが魅力といえます。
4.2 投資商品が多彩に選べる
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、前者は長期・分散投資に適した投資信託など、後者は投資信託に加え国内外株式やETFも含まれます。一括投資も可能で、iDeCoより投資対象の幅が広く、自分好みの商品を選びやすい点も強みです。
【無料】あなたに向いているのはNISA?iDeCo?3分で診断
5. iDeCoとNISAは併用できる?
5.1 違う仕組みなので同時活用OK
iDeCoとNISAは、いずれも運用益が非課税になる制度ですが、その性格は「将来年金資金の準備(iDeCo)」と「非課税枠での株式・投資信託投資(NISA)」で異なります。
要件を満たしていれば、両方同時に利用することが可能で、将来の公的年金ともあわせて老後資金を厚くできます。
5.2 併用時の注意点
iDeCoは基本的に60歳まで引き出せないため、いざという時に備えて流動性のあるNISAも上手に活用すると安心です。また、NISA枠の使い方やiDeCoの掛金設定によっては、年間で投資できる限度額があるため、計画的に拠出や投資金額を決めましょう。
6. NISAとiDeCoだけでは不十分な可能性も
6.1 運用期間が短いと貯められる金額が限られる
例えば、年利3%で毎月3万円ずつ30年間運用すると、総額は1700万円超になる計算ですが、50代で10年間しか運用しない場合は、420万円台にとどまります。複利の効果を得るには時間が必要なため、50代からのスタートだと目標に届かない可能性もあります。
6.2 インフレや物価高騰リスクに備える
今後も物価上昇が続くと、想定以上に生活費がかかる恐れがあります。iDeCoやNISAだけで心許ない場合は、債券や貯蓄型保険なども視野に入れながら、複数の手段で資産を形成・防衛することを検討しましょう。
7. 50代で投資をするときのポイント
7.1 将来必要なお金を正確に見積もる
まずは老後資金などの目標額を算出しましょう。例えば「毎月の支出-年金収入」×12ヶ月×20~25年といった基本計算で、ざっくり必要額を把握することができます。
その上で、足りない分をiDeCoやNISA、あるいは他の投資商品で補う形を検討しましょう。
7.2 リスクを抑えた商品選びが大切
50代からは安全運用がより重要です。投資信託でも海外株式中心の高リスク型ではなく、国債や国内債券を含むバランス型を選ぶ、または保険や定期預金などの元本確保型商品と組み合わせるなど、資産を守りつつ増やす戦略が求められます。
8. 一括投資を考えるなら債券や貯蓄型保険
8.1 債券への投資
国債や地方債、企業債など、債券は一般的に株式より価格変動が小さく、利子収入を定期的に得られます。満期まで保有すれば元本が返ってくる仕組みですが、発行体の信用力には注意が必要です。退職金など、まとまった資金を安定運用したい場合には選択肢の1つとして検討してもよいでしょう。
8.2 将来の保障と貯蓄を兼ねる保険
貯蓄型保険は、万が一の保障と同時に積立ができるため、貯蓄が苦手な人にも適しています。解約返戻金によって払込み保険料を上回ることもあり、個人年金保険や変額保険など、さまざまなタイプがあります。ただし、途中解約で損をするケースがあるため、商品内容をよく確認するようにしましょう。
9. よくある質問
9.1 病気や失業でiDeCoの掛金が払えなくなったら?
iDeCoは原則60歳まで引き出せませんが、掛金については減額や拠出停止が可能です。拠出を止めても口座手数料は発生し続けるため、当面の運用方針を見直して対応しましょう。
9.2 亡くなったら積立資産はどうなる?
iDeCoの資産は「死亡一時金」として、あらかじめ指定していた受取人(遺族)に支払われます。NISAの場合、非課税の優遇は亡くなった日までで終了し、残された資産は相続人の口座に移管される手続きが必要です。
9.3 NISAとiDeCoは同じ口座で運用できる?
制度上、NISA口座とiDeCo口座は仕組みが異なるため、同じ金融機関でも別々に口座を開設して管理する必要があります。一括管理はできないので注意が必要です。
9.4 毎月の投資額はどれくらいが適切?
人によって収入や生活費、目標金額は異なります。家計を圧迫しない範囲で積み立てることが基本です。将来的に追加投資やスポット投資も視野に入れつつ、少額からコツコツ始めるのがおすすめです。
10. まとめ—50代は「資産を守る」姿勢で運用を
50代からの資産形成では、若い世代ほど長期運用ができません。そのため、リスクの高い商品で大きく増やすよりも、できるだけ安全性を意識しながら着実に備えるのが重要です。
iDeCoとNISAは併用可能ですが、それぞれ税制優遇の仕組みや引き出しルールが異なるので、両者の特性を把握して賢く活用しましょう。加えて、保険や債券なども組み合わせれば、より安定感のある運用プランを構築できます。
まずは無理のない投資金額でスタートし、自分自身が納得のいく老後資金を確保することが大切です。
【無料】あなたに向いているのはNISA?iDeCo?3分で診断
参考資料
マネイロ編集部