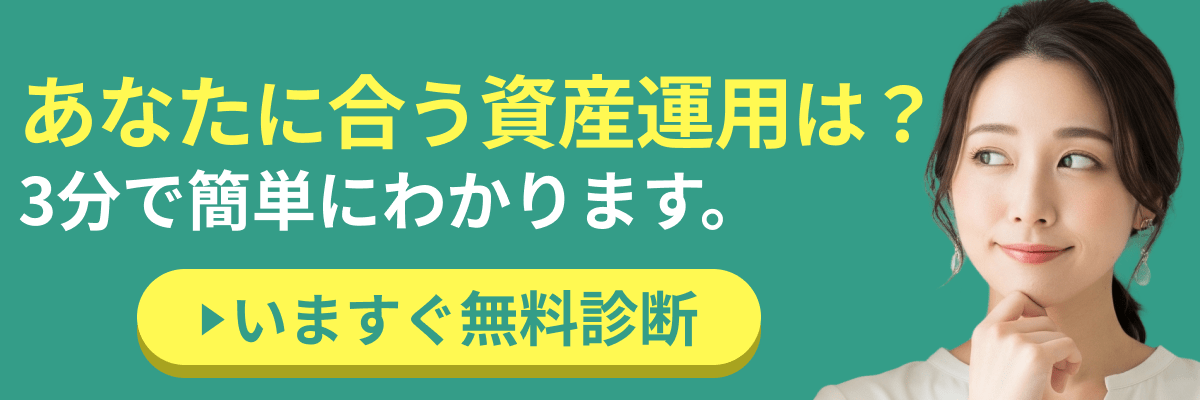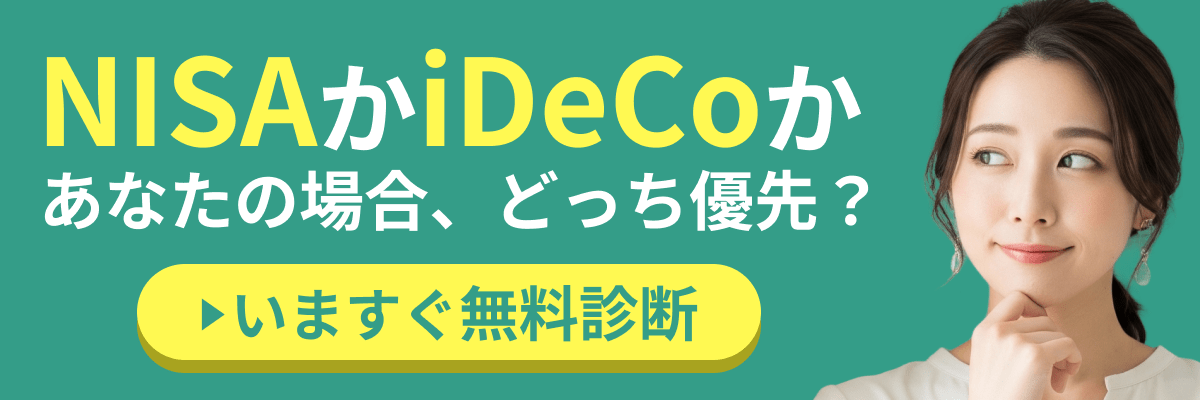投資を始めてみたいものの、何から始めればよいのかわからないという人も多いでしょう。
「新NISAやiDeCoが話題になっているから、そこからスタートすればいいのか」「預貯金に預けているだけではダメなのか」など、わからないことが多いと行動することもできないものです。
そこで本記事では、将来に備えて資産運用を始めたい方へ向けて、具体的な投資方法から失敗を避けるコツまでわかりやすく解説します。
投資への不安を解消して、着実な資産形成を目指しましょう。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
1. はじめに~資産運用の入口と重要性
資産運用とは、手元の資金を投資で運用して増やす手段のことをいいます。いまだ超低金利時代が続く日本では、預貯金だけで十分な老後資金を備えるのは難しいといわざるを得ません。
「老後2000万円問題」が話題になったことや、新しいNISAがスタートしたこともあり、資産運用を検討する人は確実に増えています。しかし、多くの人がイメージするように、投資にはリスクが伴うのも事実です。
そのため目標や目的、自分のリスク許容度をはっきりさせた上で、資産運用の方法を選択することが非常に重要です。
1.1 資産運用を始める理由
年金だけでは不安が残る老後生活に加え、住居費や医療費など、予想外の支出にも対応できるよう資産形成が求められます。特に、老後2000万円問題は「最低限の生活費」で見積もった結果であり、ゆとりある暮らしを望むなら、より多くの備えが必要です。
1.2 メリット・デメリットを整理
資産運用の大きなメリットは「お金にも働いてもらうことで、貯金以上の増やし方が見込める」点です。
一方、リスクも存在し、運用方法を誤ったり、市場の変化によっては元本割れするおそれがあるなどデメリットもあります。状況に応じて正しい判断を下すためには、一定の知識と計画性も重要になります。
2. 資産運用の代表的な種類と特徴
資産運用には多彩な金融商品が存在します。それぞれリスクとリターンの幅が異なり、自分がどの程度リスクを許容できるか認識することが重要です。
2.1 1. 預貯金
銀行や信用金庫にお金を預ける預貯金は、ローリスク・ローリターンの代表格です。預金保険制度があるため、一定額(1金融機関ごとに預金者1人あたり1000万円)までは元本が保護されます。安全性が高い一方で、現在は金利が低く、大きく増やすには向いていません。
2.2 2. 債券(円建・外貨建)
債券は国や企業が資金を集めるために発行する証券で、利子を受け取れるほか、満期で償還金を受け取ることができます。
一般的にローリスク・ローリターンとされていますが、外貨建であれば為替変動リスクが生じる場合もあります。発行体の倒産リスクや途中売却時の価格変動にも注意が必要です。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
2.3 3. 生命保険での運用
外貨建て保険
円より金利が高い通貨で運用するため、為替次第では円建て保険より返戻金が多くなる可能性があります。ただし、受取時の円転で損益が変動する点に留意が必要です。
変額保険
保険と投資信託の仕組みを組み合わせた商品です。死亡保障を確保しつつ、運用成果によって解約返戻金や保険金額が変わります。投資リスクはあるものの、うまくいけば払い込んだ保険料以上のリターンを得られる点が魅力です。
個人年金保険(変額タイプ)
一般的な個人年金に比べ、死亡保障が小さいぶん運用効率が高いタイプです。長期的に運用することで、老後の備えと一定の死亡保障を同時に得ることが可能です。ただし運用成績の変動リスクは理解しておく必要があります。
Q. 学資保険は運用向き?
学資保険は子どもの教育資金を確保する点で有用ですが、資産を増やす目的としては利率が低めです。家計に予備資金を残したい、万が一の際に備えて確実に学費を貯めたいという場合には選択肢となるかもしれませんが、資産形成に有効な商品とはいいにくいでしょう。
2.4 4. 外貨預金
日本円を外国通貨に両替して預ける外貨預金は、通貨によっては高い金利が期待できます。しかし円に再交換する際、為替レート次第で大きく元本割れするリスクもあるため、預金といっても油断は禁物です。
2.5 5. 金投資
実物資産の代表例である金に投資する方法です。金は世界的に価値が認められており、安全資産と位置づけられがちです。ただし、金利収入はなく、為替変動の影響も受けるため、全資産を金に集中させるのはリスクが高いといえます。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
2.6 6. 不動産投資
不動産を購入し、家賃収入や売却益を狙う投資です。ローンを組んで投資することが多いため、景気や相場の影響を受けやすく、空室リスクや修繕費リスクも考慮が必要です。小口化された不動産投資信託(REIT)で投資対象を分散する方法もあります。
土地を使った資産運用
土地をそのまま活用するケースとして、駐車場経営や資材置き場、太陽光発電など、あるいは建物を新築し、アパートやテナント運営を行う方法もあります。
2.7 7. 投資信託
投資信託は、多数の投資家から集めた資金を専門家が株や債券などに分散投資し、その成果を投資家に還元する仕組みです。少額から投資でき、自然と分散投資の形が取れるため、初心者でも始めやすい投資といえます。
NISA・iDeCoと投資信託
NISAやiDeCoは投資信託で得た売却益や配当金が非課税になる制度で、上手に活用すれば節税しながら資産形成できるのが強みです。ただし、iDeCoは60歳まで引き出せない、NISAは非課税枠に期限や上限があるなどの特徴を事前に確認しておきましょう。
投資信託と定期預金の使い分け
投資信託は元本保証がない一方で、長期的に高いリターンを期待できます。定期預金は安全性が高いものの、低金利の現状では増やす力に限界があります。運用の目的、資金の使途、緊急時の取り崩しなどを踏まえて使い分けるのが賢明です。
複利効果と年利
複利効果とは、元本だけでなく、運用で発生した利息部分にもさらに利息がつくことで、運用効果が雪だるま式に増す仕組みのことを指します。
年利は選択する投資商品のリスクによって異なります。一般的にリスクの高い商品は利回りも高く、リスクの低い商品は利回りも低くなります。
2.8 8. 株式
株式投資はハイリスク・ハイリターンの代表的な商品です。企業の成長にともなう株価上昇や配当金を得るチャンスがありますが、市況によっては株価が大幅に下落することもあります。長期でコツコツ運用するか、短期で売買差益を狙うか、投資スタイルの設計が重要です。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
3. 初心者におすすめの資産運用4選
初心者が比較的取り組みやすい資産運用の条件は「始めやすさ」「少額スタート」「手間の少なさ」です。これらを踏まえて、特に注目すべき4つの資産運用方法をピックアップします。
3.1 おすすめ① NISA
NISA口座を使えば、売買益や分配金にかかる20.315%の税金が非課税になります。2024年から始まった新しいNISAでは非課税保有期間が無期限になり、投資できる枠も大幅に拡大されています。
これにより、少額からでも長期目線でコツコツ積み立てながら資産運用に取り組めるようになりました。NISAは必要に応じて売却もできるため、お金の流動性を保ちたい人にも適しています。
3.2 おすすめ② iDeCo(イデコ)
iDeCoは老後資金を作るための私的年金制度です。掛金は所得控除、運用益は非課税、受取時にも退職所得控除などが適用され、節税メリットが大きい点が魅力です。
ただし、原則60歳まで資金を引き出せないデメリットもあるため、運用目的やライフプランと照らし合わせて検討する必要があります。
NISAとiDeCoの比較
・NISAはいつでも自由に引き出せる一方、iDeCoは60歳まで原則引き出せません。
・iDeCoの掛金は全額所得控除対象で、NISAよりも高い節税効果が狙えます。
・長期で放置できる資金があるならiDeCo、流動性を重視するならNISAを併用する方法もおすすめです。
3.3 おすすめ③ ファイナンシャルアドバイザーと始める投資信託
国内には数千本の投資信託があり、銘柄選びだけでも難しいもの。専門家に相談すれば、客観的な視点で投資プランを立案してもらえます。独学で迷いが生じるよりも、プロの知見を借りることで自分に合った運用をスタートしやすくなるでしょう。
3.4 おすすめ④ 運用ができる生命保険
万が一の保障を備えたい人は、運用機能付きの保険を検討しましょう。終身保険は比較的安定運用で解約返戻金が明示され、変額保険は投資信託を活用して積極的に資産形成を狙えます。長期運用と保障を同時に確保できるため、リスク分散の一環にもなるでしょう。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
4. 初心者が失敗しないためのコツ
次に、初心者が資産運用を始める際に気をつけたいポイントについて以下で解説します。
4.1 ① 目的や目標額を決める
老後資金か、教育費か、いつまでにいくら必要なのかを明確化しましょう。期間や毎月の積立額を逆算すると、自分に合った計画を立てやすくなります。
4.2 ② 「長期・積立・分散」を実践
資産運用の基本は「長期・積立・分散」です。
・長期投資:長期間保有すると複利の恩恵を受けやすい
・積立投資:ドルコスト平均法を利用し、相場の変動リスクを分散する
・分散投資:複数の通貨や地域、資産に分けて投資することでリスク軽減を図る
4.3 ③ 金融商品のリスクを理解
債券などの低リスク商品は値動きが小さく、株式などの高リスク商品は変動幅が大きい傾向があります。変動が大きいということは、儲かる幅が大きい反面、損する幅も大きいということです。自分のリスク許容度や、検討している商品の特性をしっかり理解した上で、投資先を決めましょう。
4.4 ④ 少額から始める
手持ち資金が多いからといって、いきなり大きな金額を一括投資するのはリスクが高い行為です。まとまった資金がある場合でも、何回かに分けて投資することで価格変動リスクを和らげられます。
4.5 ⑤ 価格変動に惑わされない
市場は常に上下動を繰り返します。短期的な値動きに一喜一憂するより、目標と投資方針(長期・積立・分散)がぶれていないかを確認することが大切です。過度に気持ちが揺さぶられる場合は、投資金額や方法を見直してみましょう。
4.6 ⑥ 不安なときはプロに相談
自分で調べても判断に迷う場合や継続が難しいと感じたときは、資産運用の専門家に相談するのが近道です。知識と経験が豊富なプロと一緒にプランを組み立てることで、結果的に大きな失敗を回避しやすくなります。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
5. 資産運用の始め方
5.1 STEP① 目的・目標額・運用方法を決定
ライフプランに合わせて「いつまでにどれくらいのお金を準備したいか」を明確にしましょう。老後資金や住宅資金、子どもの学費など目的によっては選ぶべき商品や運用期間が異なります。
5.2 STEP② ポートフォリオを組む
例えば「外国株式25%・国内株式25%・国内債券25%・外国債券25%」というように、複数の資産を組み合わせてリスクを調整します。一般的には年齢が若いほどリスクを取りやすいといわれています。
若い世代で投資期間が長く取れるなら、株式や、株式を対象にした投資信託の比率を高め、定年が近づくにつれて、債券など比較的安全性の高い商品の比率を高めていくのが基本です。
5.3 STEP③ 商品を選ぶ
自分のリスク許容度や運用目的に合わせて具体的な商品を選択します。
例えば、年齢が若く将来の資産づくりのために積極的に運用したいなら、NISAで株式中心の投資信託を選択、50代に差し掛かり老後資金を少しでも貯めていきたいという場合なら、iDeCoで比較的リスクの低いバランス型投信を選択する、といったように、ライフステージに応じた商品選びが大切です。
5.4 STEP④ 口座開設や保険加入の申し込み
投資信託や株式を扱うには証券会社などで口座を開設します。保険商品を利用するなら、保険会社や代理店で加入手続きをします。最近はネットで申込が完結するサービスも増えており、準備が整えば運用をスタートできます。
6. まとめ:投資初心者はNISA、iDeCoを軸に
資産運用と聞くと「難しそう」「損をしそうで怖い」と感じるかもしれませんが、正しい知識と方法で始めれば、将来に向けた心強い備えとなります。
特に投資初心者がまず活用を検討したいのが、国が用意した税制優遇制度である「NISA」と「iDeCo」です。この2つを軸に、無理なく資産運用を始めるのが成功への近道です。
自分のリスク許容度をしっかり把握した上、資産運用の基本「長期・積立・分散」を意識しながら、まずは無理のない範囲からスタートしてみましょう。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
参考資料
マネイロ編集部