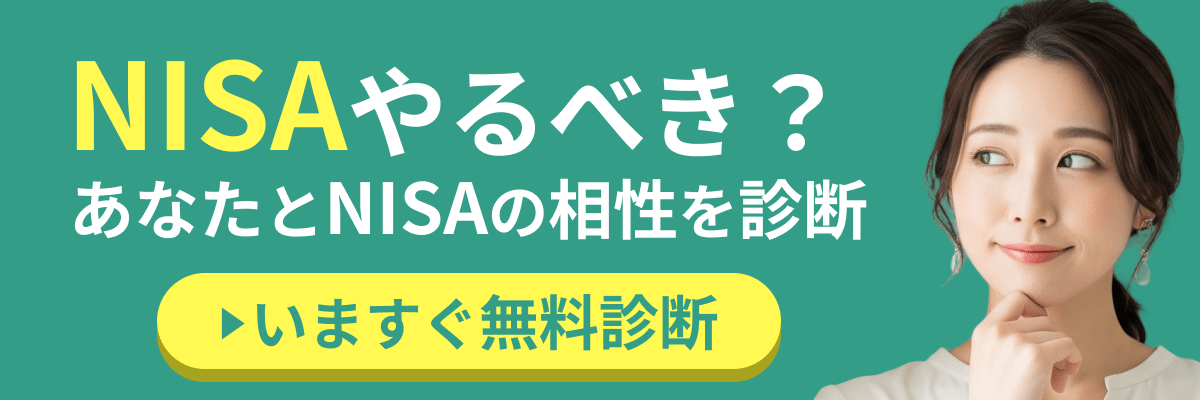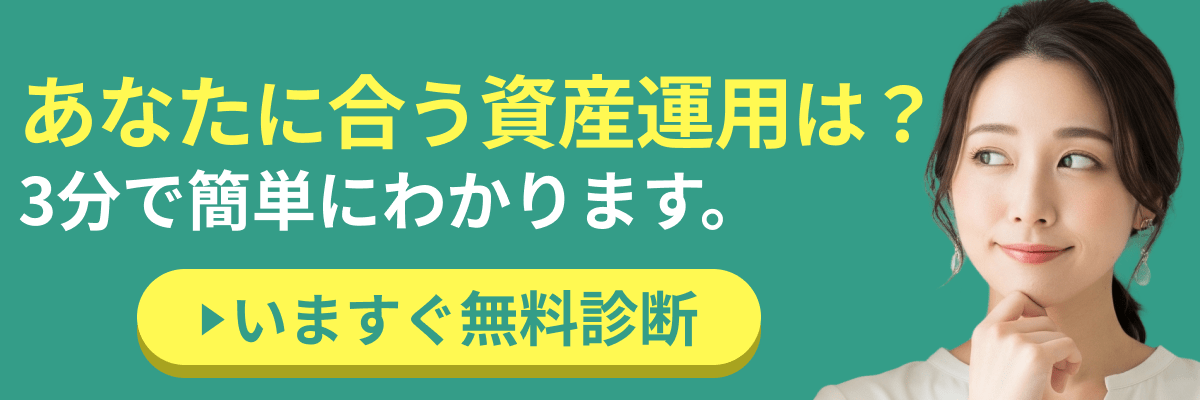「2024年に新しくなったNISAって改悪なの?」と不安に思っていませんか?
非課税保有期間が無期限化されるなど使いやすさが強調される一方で、売却判断の難しさなど新たな課題も見え隠れします。
そこで本記事ではあらためて、新しくなったNISAの特徴や注意点・デメリット、そして上手に活用するコツをわかりやすく解説します。
【無料】あなたはNISAをやるべき?最適な資産運用法を3分で診断
1. NISAとは?2024年から改正された主なポイント
1.1 つみたて投資枠と成長投資枠の併用
2023年までの旧NISAでは「つみたてNISA」と「一般NISA」が別枠で存在し、併用ができませんでした。新しいNISAでは、この両制度が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に再編され、同時利用が可能になっています。
積み立てによる長期運用と、上場株式などの成長性を狙う投資の両立がしやすくなる点が大きな特徴といえます。
1.2 投資可能額と生涯上限額の拡大
旧NISAの年間投資枠は、つみたてNISAなら40万円、一般NISAなら120万円が上限でした。これが新NISAでは「つみたて投資枠」が年間120万円、「成長投資枠」が年間240万円と大きく拡充され、合計360万円が非課税枠として利用可能となっています。
また生涯投資上限額は旧制度の800万円(つみたてNISA)から、一気に1800万円へと拡大しており、長期的な資産形成に向いています。
1.3 非課税保有期間・投資可能期間の無期限化
旧NISAでは非課税期間が最長でも20年(つみたてNISA)で、利用できる期間にも期限がありました。
しかし新NISAでは非課税保有期間が無期限化され、投資可能期間も恒久化となりました。いつからでもスタートでき、かつ売却時期を焦らずに済むため、より柔軟な運用が期待できます。
2. 新NISAが「改悪」といわれる理由
2.1 売却時期の判断がより複雑に
非課税期間の無期限化は、一見メリットに思えますが「いつ売却するか」という判断基準が曖昧になりがちです。
旧NISAなら制限時間内で売却を検討する必要がありましたが、期限がないぶん、早めに利益確定すべきか、さらに保有を続けるべきか迷いやすくなったという声も出ています。
2.2 元本保証がない点は変わらない
制度が新しくなっても、旧NISA同様、投資信託や株式などの価格変動リスクは避けられません。非課税で運用益を得られるのは大きな魅力ですが、市場が下落すれば元本割れする可能性もゼロではありません。制度が変わっても「リスクは自分で管理する必要がある」点に変わりはないでしょう。
【無料】NISAはやらないほうがいい?最適な資産運用法を3分で診断
3. 旧NISAにはない新制度のメリット
3.1 売却後に非課税枠が再利用できる
新NISAでは一度売却しても、売却額分を再度投資に回せば非課税枠を使い直すことができます。旧NISAは売却すると枠が消失してしまう仕様でしたが、新制度ではライフイベントなどで資金が必要になった場合の取り崩しと、再投資の両立が容易になります。
3.2 自由度の高さが資産形成に有利
非課税期間の無期限化や枠の再利用可能といった仕組みによって、より柔軟な対応ができるのは大きなメリットです。投資対象の商品選択肢も広く、経済状況やライフステージの変化に合わせてポートフォリオを調整しながら、長期的に資産を積み上げていけるでしょう。
4. デメリットへの対策は?
4.1 投資目標と運用期間を明確にする
売却時期の判断に迷わないためには、「投資資金をいつ、何のために使いたいのか」をはっきり決めておくことが重要です。例えば老後資金が目的なら、退職時期までにどれだけの額を用意するか逆算し、毎月の積立額を設定することで行動基準が明確になります。
4.2 万が一に備える保障の確認
投資で長期間運用するには、健康や収入面のリスクにも目を向けましょう。病気や怪我で収入が減る事態が起きると、投資を継続できなくなる恐れがあります。社会保険の給付内容や加入中の保険を確認し、不足分は民間保険などでカバーすると安心です。
4.3 長期運用を前提とした積立額の設定
新NISAは年間最大360万円まで非課税投資が可能ですが、必ずしも上限まで使う必要はありません。無理のない範囲で毎月コツコツ続けるほうが、長期的な複利効果を活かしやすくなります。余裕が生まれたタイミングで積立額を増やすなど、柔軟に調整するとよいでしょう。
4.4 専門家へ相談して不安を解消する
投資経験が浅いと、株式や投資信託の商品選択や売却のタイミングに悩むケースが多くなるでしょう。もし判断に迷ったときは金融機関やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、客観的なアドバイスを得ると失敗を防ぎやすくなります。
5. NISAを始めるなら今がおすすめ
NISAは投資初心者でも始めやすい非課税制度ですが、その恩恵を最大限受けるには「長期にわたって運用を続ける」ことが鍵です。
市場が上下動しても時間的な余裕を生かして回復を待ちやすく、複利による資産増加効果も期待できます。
早めに開始し、将来への準備を着実に進めましょう。
6. まとめ
新NISAは非課税保有期間の無期限化や投資可能額の拡大など、大きなメリットがある一方、自由度が高まる分だけ投資判断の難易度も上がります。
だからこそ、投資の目的や目標額、商品の選び方、売却の判断基準をしっかり決めておくことが大切です。困ったときは専門家へ相談し、無理のない長期運用を続けることで、新NISAの恩恵を十分に受けられるでしょう。
【無料】あなたはNISAをやるべき?最適な資産運用法を3分で診断
参考資料
マネイロ編集部