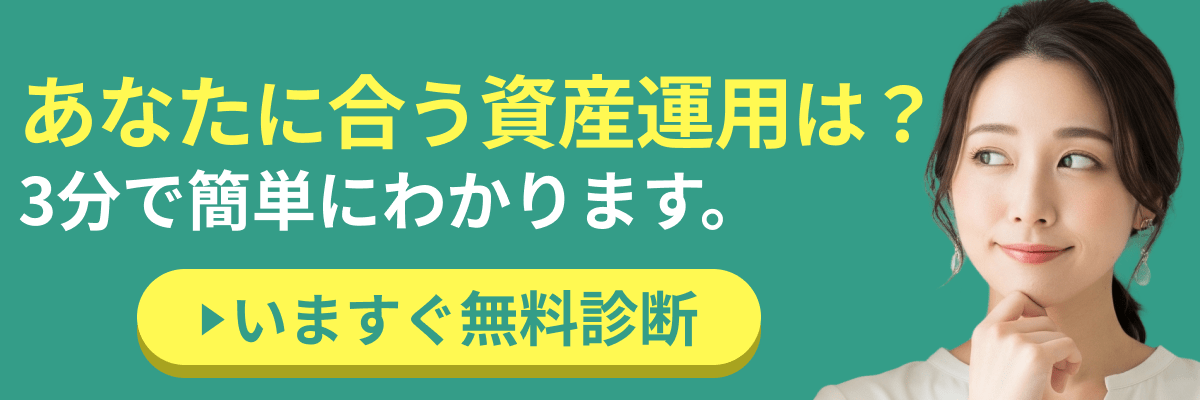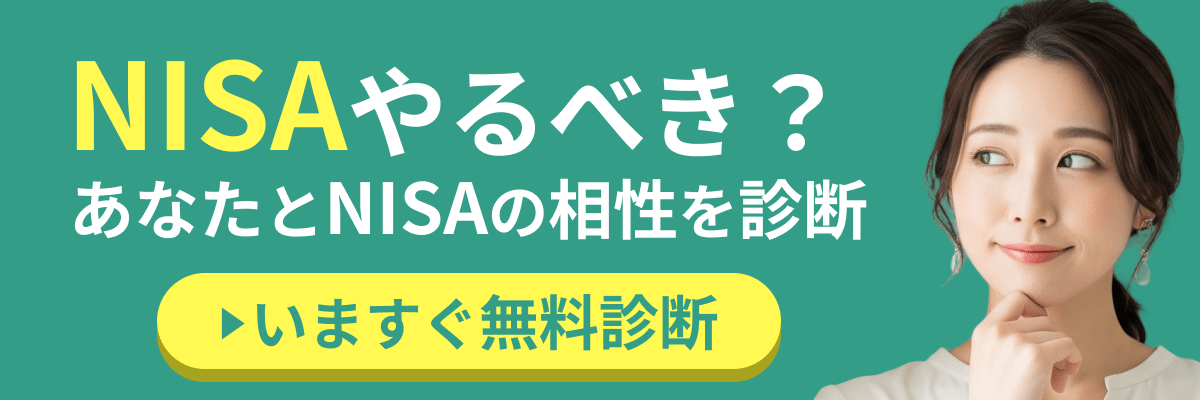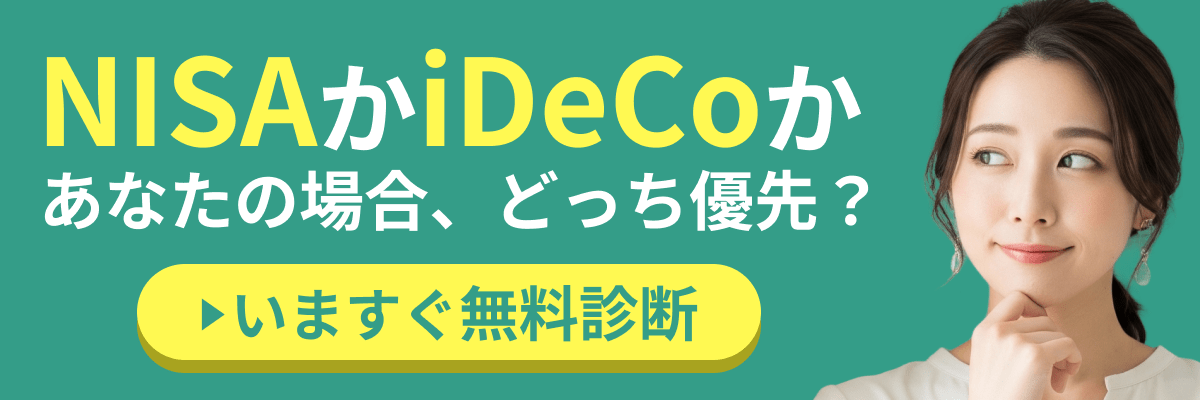将来のために投資を始めたいけれど、どの制度が自分に向いているか迷う人は多いでしょう。
2024年からスタートした新しいNISAと、私的年金のiDeCoは比較されることが多く、特にこの2つの制度の使い分けについて悩む人もいることでしょう。
今回はこの2つの制度を同時に利用するメリットや注意点、活用術を、幅広い年代・職業別にわかりやすく解説します。
【無料】あなたに向いているのはNISA?それともiDeCo?3分で診断
1. 積立投資がおすすめな理由
長期的な資産形成を目指す上では、定期的に積み立てて投資するスタイルが基本となります。投資先が値上がりしたり配当を生み出したりすれば、複利の力によって資産が効率的に増えていく可能性があります。
また、毎月一定額を積み立てることで、後述の「ドル・コスト平均法」の効果を活かし、取得単価を平準化できます。これにより、市場の変動による影響をやわらげる効果も期待できます。
1.1 複利効果とは
複利とは、得た利益を元本に組み入れて再運用することで、元利合計が雪だるま式に増える仕組みのことを指します。長期で積立投資を行うことで複利効果を最大化でき、資産が効率的に増える可能性が高まります。
1.2 ドル・コスト平均法を活かす
値動きのある金融商品に対して、一定の金額を定期的に投資する手法を「ドル・コスト平均法」といいます。価格が高いときには少ない口数を、安いときには多くの口数を購入できるため、平均購入単価を平準化できるというメリットがあります。
相場の先行きを読むのはプロでも難しいため、金額を決めて着実に積み立てていくことが、長期的な資産形成のポイントとなります。
2. NISA(ニーサ)とは
NISAは、配当金や売却益といった投資の運用益が非課税になる税制優遇制度です。
2.1 非課税になる範囲は?
NISA口座内で得た利益(分配金や売却益)が非課税になります。通常20.315%かかる税金がゼロになる、資産形成を行う上で非常に有利な制度です。
年間投資枠は「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円の合計最大360万円で、生涯の非課税保有限度額は1800万円です。2024年から非課税保有期間が無期限となったことで、長期的な資産形成の核となり得る制度となっています。
2.2 どんな商品に投資できる?
「つみたて投資枠」では、金融庁が定めた長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託やETF(上場投資信託)に投資できます。
一方、「成長投資枠」では、それらに加えて個別株式など、より幅広い商品が対象となります。この2つの枠は併用できるため、柔軟な商品選択が可能です。
2.3 コストと積立金額の柔軟性
NISA口座の開設・管理に手数料はかかりませんが、投資信託の信託報酬などは発生します。積立金額は金融機関によって月々100円や1000円といった少額から設定でき、いつでも変更・停止が可能です。
また、NISA口座内の商品を売却した場合、その商品の簿価(取得価額)分の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できる点も大きな特徴です。
3. iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出して運用し、老後資金を作る私的年金制度です。
3.1 どこが非課税になる?
iDeCoは私的年金制度で、掛金が全額所得控除になるほか、運用中の利益も非課税となります。さらに60歳以降の受取時も退職所得控除や公的年金等控除を活用できるため、節税効果は非常に高いといえます。
ただし、原則として60歳まで資金を引き出せない点には注意が必要です。
3.2 投資できる商品は?
iDeCoでは、金融機関ごとに異なるラインナップの投資信託や保険商品、定期預金を扱っており、国内外の株式や債券、不動産投信など、多様な投資先から選択できるのが特徴です。
中には、アクティブファンドやバランス型などもあり、自分のリスク許容度に合う商品を選びやすいメリットがあります。
【無料】あなたはNISAをやるべき?それともiDeCo?3分で診断
3.3 コストと金額変更について
iDeCoでは、国民年金基金連合会への手数料や金融機関への管理料などが必ずかかります。加入時や掛金拠出時、給付を受け取る際など複数のタイミングで費用が発生する仕組みです。
また、年1回まで拠出額を変更できますが、掛金の拠出を停止しても管理手数料を支払い続ける必要がある点は注意が必要です。
3.4 途中解約や転職時の扱い
iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、基本的に緊急時の資金としては使えません。
また、転職で企業型DCがない職場に移る場合、6ヶ月以内にiDeCoへ移換手続きを行わないと資産が自動移換され、運用が停止し手数料だけが引かれるリスクがあります。転職時には手続きを忘れないよう気を付けましょう。
4. NISA・iDeCoで運用する投資信託とは
投資信託とは、多数の投資家が出資した資金を運用の専門家がまとめて株式や債券、不動産などに投資する金融商品です。
中には1本のファンドで世界中に分散投資できるものもあり、少額から始められるため、初心者にも取り組みやすい点が魅力といえます。運用方針は目論見書に記載されており、購入前に内容を確認しておくことが重要です。
5. NISAとiDeCoを併用する時の活用法【年代別・職業別】
両制度とも投資にはリスクがあるため、まずは「生活防衛資金」を現預金で確保してから始めるのがおすすめです。生活防衛資金は、生活費の半年程度を目安に準備できると安心でしょう。
また、病気やケガなど万が一の際に備え、医療保険や所得補償保険などで対策を整えておくことも大切です。
5.1 年代別の活用法
20代で始めるなら
20代は長期運用の利点を最大限に活かせます。20代では貯蓄が十分に準備できていないケースも多いため、まずはいつでも引き出せるNISAのつみたて投資枠から少額で始めるのがよいでしょう。慣れてきたら、節税効果の高いiDeCoの活用も検討するのがおすすめです。
非課税期間が無期限になったNISAは、20代からコツコツ始めることで絶大な複利効果が期待できます。
30代は投資と保障の両立を
結婚や住宅購入などライフイベントが多い30代は、教育資金や老後資金など目的別に計画的な準備が必要です。
資金を引き出しやすいNISAを教育資金作りの「一部」として活用しつつ、老後資金のコアとしてiDeCoを併用するのが効果的です。同時に万一に備え、生命保険や医療保険などで家族のための保障も整えておきましょう。
【無料】あなたに向いているのはNISA?それともiDeCo?3分で診断
40代こそ早めの準備
老後が近づくにつれ、資産形成にかけられる時間が短くなってきます。とはいえ、40代からでも長期投資の時間は十分にあります。まずは非課税期間が無期限のNISAを積極的に活用し、老後資金を着実に準備しましょう。
iDeCoの掛金拠出は65歳になるまで可能なので、40代で始めるなら負担とリターンを冷静に見極めつつ検討するとよいでしょう。また、この時期は健康状態の変化にも注意し、保険の見直しも検討するのがおすすめです。
50代からでも遅くない
50代からでもNISAでの資産形成は遅くありません。非課税期間の縛りがなくなったため、退職時期に合わせて柔軟な計画を立てられます。
NISAを主軸に据えつつ、節税を考えてiDeCoの拠出も検討しましょう。ただし、iDeCoは受取開始が60歳以降になるため、自身の資金計画と照らし合わせて慎重に判断しましょう。
5.2 職業別の活用法
自営業
公的な年金が少ない自営業者にとって、iDeCoは老後資金作りの必須ツールです。掛金の上限も月額6万8000円と高く、全額所得控除になるメリットは絶大です。それに加えて、事業用の資金繰りなども考慮し、流動性の高いNISAを併用することで、より盤石な資産形成が目指せます。
会社員
まずは勤務先の企業年金制度(企業型DCやDBなど)を確認しましょう。その上で、老後資金に不安があれば、まずは自由度の高いNISAの活用がおすすめです。iDeCoも節税メリットが大きく有効ですが、転勤や転職時の手続きも念頭に置いておきましょう。
公務員
公務員は2024年12月以降、iDeCoの掛金上限が月2万円に引き上げられましたが、退職金や共済年金が充実している場合は、手数料を考慮してiDeCoにこだわらないという選択も一つの考え方です。NISAのつみたて投資枠や特定口座をうまく活用し、さらに余裕があればiDeCoの追加も検討するとよいでしょう。
パート主婦(夫)
所得税・住民税を納めていない場合、iDeCoの所得控除のメリットは受けられません。そのため、非課税で運用でき、いつでも引き出せるNISAが最適な選択肢となります。扶養の範囲内で働きながら、NISAのつみたて投資枠を使ってコツコツ資産を育てるのがおすすめです。
5.3 運用スタイルごとの活用例
インデックスファンドとアクティブファンドの違い
投資信託には、市場指数に合わせた運用を目指すインデックスファンドと、市場を上回る成果を狙うアクティブファンドがあります。
インデックスファンドは手数料が低い傾向にあり、アクティブファンドは運用担当者の独自調査や銘柄選定がある分、手数料が高めです。投資目的やリスク許容度に合った運用を選びましょう。
活用方法①両ファンドを使い分ける
NISAの「つみたて投資枠」ではインデックスファンドに堅実に積み立て、「成長投資枠」で、高いリターンを狙うアクティブファンドを取り入れる方法があります。ただし、アクティブ商品はリスクが高いため、特に投資初心者は慎重に検討をしたほうがよいでしょう。
活用方法②異なる指標を分散する
もし、どちらもインデックス中心にしたい場合は、同じベンチマークに偏らないよう工夫するとよいでしょう。
例えば、つみたて投資枠で全世界株式、iDeCoで先進国債券を選ぶなど、異なる指標に資金を配分することでリスク分散ができます。
6. 長期運用するなら「長期的に成長する資産へ投資」
長期投資を考える場合、世界経済の成長を取り込める資産に投資するのが有力な選択肢となります。なかでも世界株式は、人口増加や技術革新に伴って企業価値が高まる可能性があり、長期的なリターンが期待できます。
実際に、過去のデータでは世界全体のGDPや株価は長期的に成長してきた傾向があり、長期間にわたって運用することで短期的な価格変動の影響を緩和できる可能性もあります。
7. NISAとiDeCo、自分に合う金融機関の選び方
7.1 ネット証券が向いている人
自力で商品を調べ、コストを最小限に抑えたいならネット証券がおすすめです。手数料が安く、商品数も豊富ですが、対面サポートはほとんどないため、自己責任で判断できる人向けといえます。
7.2 店舗型金融機関が向いている人
窓口で担当者に直接相談しながら進めたいなら、銀行や証券会社の店舗型が安心です。対面サポートを受けられる分、ネット証券より手数料がかかる場合もありますが、商品選びに不安がある初心者や詳しい説明が欲しい方に向いています。
7.3 IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が向いている人
金融機関に属さないIFAは、投資の提案から売買の手続き、継続的なフォローまで個別に対応してくれます。長い期間、担当が変わらないケースが多く、ライフプランの変化に合わせて柔軟な助言を受けたい人に適しています。
8. まとめ:NISAとiDeCoを上手に活用しよう
NISAとiDeCoは、税制優遇を受けながら資産形成を進められる便利な制度です。
これらを上手に活用するには、いつでも引き出せる自由度の高いNISAと、強力な所得控除があるものの60歳まで引き出せないiDeCo、それぞれの特徴を理解することは欠かせません。
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分の年代や職業、運用スタイルに合わせて賢く組み合わせ、無理のない範囲で長期的な資産づくりを始めましょう。
【無料】あなたに向いているのはNISA?それともiDeCo?3分で診断
参考資料
マネイロ編集部